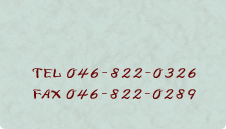人の一生とお菓子
\r\n 人はこの世に生を受けてから成長するに従い、さまざまなお祝いをしたり儀式をおこなったりして、そのときどきの状況に応じた、節目ある生活を送っています。
人はこの世に生を受けてから成長するに従い、さまざまなお祝いをしたり儀式をおこなったりして、そのときどきの状況に応じた、節目ある生活を送っています。\r\n幼いときは、両親や周囲の人々の庇護を受け、やがて独立し家庭をもうけて、親からの日常の風習を引き継ぎ生活をするようになります。
\r\n近年、原点にかえれ、といわれて古きよき日本の風習が見直され、受け継がれる傾向があるのはまことによろこばしいことです。
\r\n\r\n
慶事とお菓子
\r\n| \r\n帯祝い\r\n | \r\n五ヶ月目の戌の日に、この岩田帯を締める風習が今もあります。\r\n犬は多産で、そのうえ、お産が軽いということから起こったことと思われます。\r\n | \r\n帯締め団子\r\n |
|---|---|---|
| \r\n三つ目\r\n | \r\n生まれて、三日目におはぎを食べる風習があります。お米を食べると母乳の出が良くなるということからだと思われます。それと同時にお世話になった方々に、誕生の報告をして祝います。\r\n | \r\n三つ目のおはぎ\r\n |
| \r\nお宮参り\r\n | \r\n男子三十二日目、女子三十三日目、祖母が赤ちゃんを抱いて参詣するのが一般的です。\r\n | \r\nお赤飯・紅白まんじゅう・鶴の子餅・鳥の子餅\r\n |
| \r\n初節句\r\n | \r\n誕生して最初に迎える節句で、女子は三月三日(桃の節句)、男子は五月五日(端午の節句)にお祝いします。\r\n | \r\n桃の節供~菱餅・さくら餅・草餅・三色餅・雛あられ・ケーキ \r\n端午の節句~柏餅・ちまき・ケーキ\r\n |
| \r\n初誕生\r\n | \r\n初めての誕生日。一升の餅を誕生餅として子どもに背負わせる風習があります。初誕生を祝い、いっそうのすこやかなる成長を祈ります。\r\n | \r\n誕生餅・お赤飯・ケーキ\r\n |
| \r\n七五三\r\n | \r\n産まれた土地の産土(うぶすな)神社にお参りして子の幸運を祈ります。(男の子・五才、女の子・三才・七才)\r\n | \r\n千歳飴・お赤飯・鳥の子餅・ケーキ\r\n |
| \r\n入学・ 卒業\r\n | \r\n子供よ、若竹のように自由に元気ですくすく伸びておくれと、子を思う親の切なる願いと周囲の暖かい心がこのお祝いに託されています。\r\n | \r\nお赤飯・お餅・紅白饅頭・ケーキ\r\n |
| \r\n成人式\r\n | \r\n一月十五日・この日から自分の生き方に責任をもって生きなければいけない満二十歳に達した男女を励まし祝う儀式です。\r\n | \r\nお赤飯・お餅・ケーキ・紅白饅頭\r\n |
| \r\n就職祝\r\n | \r\nいよいよ社会人として巣立つ日です。夢を大きくもって、挫折を恐れずはばたいてほしいものです。\r\n | \r\nお赤飯・紅白饅頭・鳥の子餅・ケーキ\r\n |
| \r\n結婚\r\n | \r\n人の一生における大切な転機といえる結婚は、一組のカップルが社会の仲間入りをして、子々孫々の繁栄の道を共に歩んでいくことを誓う意識の深い祝事です。\r\n | \r\nお赤飯・引き菓子・ケーキ・焼菓子\r\n |
| \r\n長寿祝\r\n | \r\n六十歳還暦、七十歳古希、七十七歳喜寿、八十歳傘寿、八十八歳米寿、九十歳卆寿、九十九歳白寿。それぞれのスタイルに味わいをもって人生をつくり上げた先輩の方々に、この日は心からの祝福を送りたいものです。\r\n | \r\nお赤飯・引き菓子・お餅・紅白饅頭・カステラ・鶴の子餅\r\n |
| \r\n上棟祝・新築祝\r\n | \r\n家屋の骨組みができると、上棟式を行います。\r\n | \r\nお供え餅・お赤飯・投げ餅\r\n |
| \r\n敬老の日\r\n | \r\n九月十五日は敬老の日です。この日はお年寄りの長寿を祝い、また各々がやがて訪れるであろう我が身を顧み、老人の福祉について考えたい日でもあります。平均寿命ものびて、お年寄りといっても、若やいだ雰囲気がありますから、一層その気持ちを大切にするように周囲の人が気を配ってあげたいものです。\r\n | \r\nお赤飯・紅白饅頭・カステラ\r\n |
仏事・法要とお菓子
\r\n人生は生者必滅でありますので、一生を閉じたときには丁重に弔い、年忌ごとの供養は子孫の務めですので、心をこめて営みたいものです。\r\n| \r\n通夜・ 告別式\r\n | \r\n死亡したとき、親族、友人、知己の見舞いを受けて通夜が営まれます。\r\n宗派の儀式によって手厚く葬られます。\r\n | \r\n法立盛り菓子・施主餅・供養餅・通夜饅頭・焼饅頭\r\n |
|---|---|---|
| \r\n立日 (出日)\r\n | \r\n病気見舞の返礼をすませず亡くなったときには三十日目に立日(出日)としてお返しをします。\r\n | \r\n焼饅頭・青白饅頭・おはぎ\r\n |
| \r\n法要\r\n | \r\n故人の追善供養を営む時は、毎日あわただしく暮らしている時には考えてもいない様々なことを生者必滅という感慨をもって行いたいものです。\r\n | \r\n四十九餅・春日饅頭・青白饅頭・引き菓子\r\n |
| \r\n年忌\r\n | \r\n仏式亡後七日 三十五忌 四十九忌 一年期年忌 三年忌 七年忌 十三年忌 三十三年忌 五十年忌\r\n | \r\n仏式引菓子・青白饅頭・焼饅頭\r\n |
一年間の行事の中のお菓子
\r\n| 一月 | \r\n御年賀:新年の挨拶をする | \r\n御進物菓子折 | \r\n
|---|---|---|
| 二月 | \r\n節分:家運の繁栄を祈り豆まきをする \r\n 初午:初の午の日方策を祈る | \r\n 豆餅・赤飯・袋菓子 | \r\n
| 三月 | \r\n彼岸:先祖の霊をうやまう \r\n 桃の節句 | \r\n おはぎ・彼岸だんご・焼まんじゅう・打菓子 \r\n 雛あられ | \r\n
| 四月 | \r\n御花見 | \r\nだんご・桜もち | \r\n
| 五月 | \r\n端午の節句 | \r\n柏餅・ちまき | \r\n
| 六月 | \r\n夏向き菓子の衣替え | \r\n\r\n |
| 七月 | \r\n御中元・七夕まつり・お盆・先祖の霊をお迎えする | \r\n迎えだんご・送りだんご・おはぎ・お供え・赤飯 | \r\n
| 八月 | \r\n旧盆・ふるさとの帰省みやげに | \r\n横須賀菓子銘菓 | \r\n
| 九月 | \r\n十五夜 \r\n 彼岸 | \r\n 月見だんご・月見まんじゅう \r\n おはぎ・彼岸だんご・打菓子 | \r\n
| 十月 | \r\n十三夜 | \r\n月見まんじゅう | \r\n
| 十一月 | \r\n七五三・祝月で種々祝事の返礼をする 酉の市 | \r\n 千歳飴・赤飯 きんつば・きりざんしょ | \r\n
| 十二月 | \r\nお歳暮 | \r\n二十五日頃より新年を祝うのし餅 \r\n 御進物菓子折・新年祝餅・お供え | \r\n